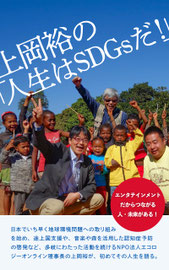その名の通り、背中の「コブ」が2つあるのが特徴。
人間の乱獲、オオカミの群れによる捕食など、さまざまな原因で野生のラクダの数は激減している。
野生のラクダは驚くほど強健で、彼らのコブは、水や食物が手に入らないときに水分とエネルギーに変換される脂肪を蓄積する機能を果たす。
このコブのおかげで厳しい砂漠環境でも、水なしで長期間移動できる。
妊娠期間は約13ヶ月と長いため、野生のラクダの個体数の回復には時間がかかる。
コピー・イラスト / kawe
www.eco-online.org Blog Feed
「‘‘ニホン’’イタチ」なのに外来種?! (木, 08 2月 2024) ニホンイタチ / Japanese weasel
ニホンイタチってどんな動物?
日本には、ニホンイタチとシベリアイタチが生息しています。
今回取り上げるのは、ニホンイタチ。シベリアイタチと比べると体は一回り小さく、尻尾が短いのが特徴です。
このシベリアイタチとの生存競争に負けてしまったために、生息数が減り、絶滅危惧種になってしまったと言われています。
↓シベリアイタチについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
外来種だけど絶滅危惧?!対馬の「シベリアイタチ」
平均寿命は1.9歳。シベリアイタチと同じく、とても短いですね。
体長は、オスが27-37cm、メスが16-25cm。
尾の長さは、オスが12-16cm、メスが7-9cm。
体重は、オスが290-650g、メスが115-175g。
こんな感じで、オスとメスで体の大きさにかなりの違いがあります。
一夫多妻制で泳ぐことも得意。川や湿地など、水辺に近い場所に生息しています。
主に食べるのはネズミや鳥類、両生類、昆虫、魚類など。植物も食べます。
魚を捕らえる貴重な動画がありました。埋め込みができないようなので、気になる方は下のリンクから見に行ってみてください。(YouTubeへのリンクです)
「日本の動物 魚を襲うニホンイタチ」
https://youtu.be/R2AGcS2xeKk?si=vS22EJnax79Hy8_V
「日本の動物 水中(underwater)で魚を捕食するニホンイタチ」
https://youtu.be/pFHTjCdSY6g?si=88PqWZtjvJ1PWw1Q
イタチといえば、2本足で立って周りを伺う姿が印象的です。かわいいですね。
ここでイタチが関係している言葉をひとつ。
みなさん、太陽の光が眩しい時に、手を目の上にかざして遠くを見たことがありますよね?
イタチが人を見る時にも同じ行動をするという俗信があり、そこから、疑わしげに人を見るようすを「鼬(いたち)の目陰(まかげ)」と言うようになったそうです。
日本固有種のニホンイタチが、沖縄県では侵略的外来種に?!
ニホンイタチはもともと、本州、四国、九州などに分布していましたが、農業被害などをもたらすネズミ類への対策のため、北海道や伊豆諸島南部、南西諸島、沖縄県などに導入され、今では日本全域に分布しています。
沖縄県のいくつかの島では、ニホンイタチが導入されたことで、在来動物の個体数が減少・絶滅してしまった可能性があるということも言われています。
稀少な爬虫類や両生類が捕食されており、沖縄県では、ニホンイタチが生態系に重大な悪影響を及ぼすとして、「沖縄県対策外来種リスト」の中でも優先順位の高い「重点対策種」として指定。
さらに、シベリアイタチと同じ「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定されています。
<ここでちょっと解説>
■日本の固有種がなんで外来種になるの?
外来種とは、人間によって生息していない地域に持ち込まれた生き物のことです。
外国から日本へ持ち込まれた生き物だけでなく、例えば本州から北海道へ、北海道から九州へ、、
といった具合に、日本国内の島から島へ運ばれた生き物も、外来種ということになります。
そのため、日本の固有種であるニホンイタチも外来種になることがあります。
■「沖縄県対策外来種リスト」とは?
沖縄県では、島ごとに多くの固有種が生息しており、日本全体の中でも生物多様性の高い地域です。
そこで、沖縄県固有の生き物、そして人や農林水産業などを守るために「沖縄県対策外来種リスト」というものを出しています。
コピー・イラスト / kawe
ニホンイタチ / Japanese weasel
ニホンイタチってどんな動物?
日本には、ニホンイタチとシベリアイタチが生息しています。
今回取り上げるのは、ニホンイタチ。シベリアイタチと比べると体は一回り小さく、尻尾が短いのが特徴です。
このシベリアイタチとの生存競争に負けてしまったために、生息数が減り、絶滅危惧種になってしまったと言われています。
↓シベリアイタチについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
外来種だけど絶滅危惧?!対馬の「シベリアイタチ」
平均寿命は1.9歳。シベリアイタチと同じく、とても短いですね。
体長は、オスが27-37cm、メスが16-25cm。
尾の長さは、オスが12-16cm、メスが7-9cm。
体重は、オスが290-650g、メスが115-175g。
こんな感じで、オスとメスで体の大きさにかなりの違いがあります。
一夫多妻制で泳ぐことも得意。川や湿地など、水辺に近い場所に生息しています。
主に食べるのはネズミや鳥類、両生類、昆虫、魚類など。植物も食べます。
魚を捕らえる貴重な動画がありました。埋め込みができないようなので、気になる方は下のリンクから見に行ってみてください。(YouTubeへのリンクです)
「日本の動物 魚を襲うニホンイタチ」
https://youtu.be/R2AGcS2xeKk?si=vS22EJnax79Hy8_V
「日本の動物 水中(underwater)で魚を捕食するニホンイタチ」
https://youtu.be/pFHTjCdSY6g?si=88PqWZtjvJ1PWw1Q
イタチといえば、2本足で立って周りを伺う姿が印象的です。かわいいですね。
ここでイタチが関係している言葉をひとつ。
みなさん、太陽の光が眩しい時に、手を目の上にかざして遠くを見たことがありますよね?
イタチが人を見る時にも同じ行動をするという俗信があり、そこから、疑わしげに人を見るようすを「鼬(いたち)の目陰(まかげ)」と言うようになったそうです。
日本固有種のニホンイタチが、沖縄県では侵略的外来種に?!
ニホンイタチはもともと、本州、四国、九州などに分布していましたが、農業被害などをもたらすネズミ類への対策のため、北海道や伊豆諸島南部、南西諸島、沖縄県などに導入され、今では日本全域に分布しています。
沖縄県のいくつかの島では、ニホンイタチが導入されたことで、在来動物の個体数が減少・絶滅してしまった可能性があるということも言われています。
稀少な爬虫類や両生類が捕食されており、沖縄県では、ニホンイタチが生態系に重大な悪影響を及ぼすとして、「沖縄県対策外来種リスト」の中でも優先順位の高い「重点対策種」として指定。
さらに、シベリアイタチと同じ「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定されています。
<ここでちょっと解説>
■日本の固有種がなんで外来種になるの?
外来種とは、人間によって生息していない地域に持ち込まれた生き物のことです。
外国から日本へ持ち込まれた生き物だけでなく、例えば本州から北海道へ、北海道から九州へ、、
といった具合に、日本国内の島から島へ運ばれた生き物も、外来種ということになります。
そのため、日本の固有種であるニホンイタチも外来種になることがあります。
■「沖縄県対策外来種リスト」とは?
沖縄県では、島ごとに多くの固有種が生息しており、日本全体の中でも生物多様性の高い地域です。
そこで、沖縄県固有の生き物、そして人や農林水産業などを守るために「沖縄県対策外来種リスト」というものを出しています。
コピー・イラスト / kawe
>> 続きを読む
かわいい「ラッコ」はどこへ行った!? (Tue, 30 Jan 2024)
 ラッコ / 海獺 / Sea otter
水族館で人気のラッコが、絶滅危惧種?!
その可愛さからもファンが多いラッコ。
水族館などでよく見るイメージがあるかと思いますが、実はラッコは、絶滅危惧種のレッドリストの中でも絶滅の危険が非常に高い「絶滅危惧IA類」に指定されています。
水族館で見られるラッコも、今ではかなり少なくなってきています。
ラッコってどんな動物?
ラッコは、北アメリカとアジアの太平洋沿岸に生息しています。
日本では、北海道で見ることができます。
体重は約15〜45kg、体長は約100〜150cm。
平均寿命は、野生では約15年、飼育下では約20年です。
鼻はひし形で、尾は平べったい形。
水の中に入っているときは、鼻と耳を閉じることができます。
顔の毛の色は赤ちゃんの頃は茶色ですが、3歳を過ぎる頃から、年齢を重ねるにつれだんだん白くなっていきます。
わきの下のたるみをポケットのようにして、お気に入りの石や食べきれなかった貝などをしまいこむ癖があります。
鳥羽水族館YouTubeにわかりやすい動画がありました。
ラッコは海の沿岸部や、海岸から1km以内の場所に生息しており、一生のほとんどを海の中で過ごします。
食事をしたり眠ったりするときには、流されないように海藻を体に巻き付けたり、つかまったりするそうです。
ラッコ同士、手を繋いで休むことも。
水族館でも手を繋いでいる姿は大人気。誰もがメロメロになってしまう可愛さですね。
ラッコは食いしん坊?
ラッコは肉食で、主に貝類や甲殻類、ウニ類などを食べます。魚類や海鳥を食べることもあります。
皮下脂肪が少ないため、体温を維持するために1日に体重の約4分の1〜5分の1の量の食べ物を食べる必要があります。
ラッコは30kgほどなので、1日に約6〜9kg食べなければなりません。
これは、50kgの人間に置き換えると、1日に10〜15kgも食べるということになります。
驚きの量ですが、ラッコはただの食いしん坊ではなく、生きるために食べているのですね。
そしてラッコと言えば、貝などの硬い食べ物をお腹の上に乗せた石に叩きつけて割り、中身を食べる行動が有名ですが、住む地域によっては叩きつける必要がないものを食べるため、この行動をしないラッコもいます。
水族館では、展示用のガラスや石に叩きつけて割ることも多いようですが、なんと2009年には、愛知県の豊橋総合動植物公園で飼育されていたラッコのヤヨイ(メス・15歳)が、数年にわたりエサの貝殻をガラスに打ち付けて食べていたところ、とうとうガラスも耐えられなくなり、強化ガラスであるにも関わらずヒビが入ったことがあるそうです。
ラッコの力を侮ることなかれ。。
ラッコにとって大切な、毛皮と毛づくろい
全身に約8億本もの体毛が生えているラッコ。
特にお腹の毛は、ほ乳類の中でも密度がとても高いと言われています。
ちなみに、人間の体毛は500万本、髪は10万本だそうです。ラッコ、すごい。
しかし、すごいのは毛の多さだけではありません。
毛づくろい(グルーミング)をして毛と毛の間に空気の層をつくり、冷たい水が直接皮膚に触れないようにすることで、体温を保つことができるのです。
Xで話題になったこのほっぺたをむにむにする可愛い仕草も、毛づくろいだそうです。
https://x.com/mayu_kko/status/1556097751934726145?s=20
冷たい水の中でもラッコが生きられるのは、この毛のおかげなのです。
毛が汚れてしまうと、体温をうまく調節できなくなってしまうため、ラッコは1日5〜6時間も毛づくろいをしなくてはいけません。
この優れた保温機能を求めて、毛皮を目的にラッコは世界中で乱獲されてしまいます。
日本でも平安時代から乱獲され、絶滅寸前にまで数が減ってしまいました。
そこで、明治時代の1912年には、ラッコやオットセイの捕獲を禁止する「臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)」が公布されました。
乱獲されたり、漁業の網にかかってしまったり、タンカー事故で流出した原油の被害にあったり、世界中でラッコの生息数が減ってしまった原因には、いろいろなものがあります。
現在、水族館で会えるラッコは3頭のみ!
1982年、アラスカから静岡県の「伊豆・三津シーパラダイス」に初めてラッコが来ました。
1984年に三重県の「鳥羽水族館」で日本初のラッコの赤ちゃんが誕生したことから、ラッコブームが始まったと言われています。当時は3時間の行列ができるほどの人気ぶりだったそう。
しかしその後、ラッコの個体数が減ったために、ワシントン条約で国際取引が禁止とされました。
水族館での繁殖も難しいため、日本の水族館ではラッコがどんどん減っている状況です。
ピークである1994年には122頭が飼育されていましたが、2024年1月現在、日本国内で見られるのは3頭のみとなっています。
そのうちの2頭が、三重県の「鳥羽水族館」、
1頭が、福岡県の「マリンワールド海の中道」で飼育されています。
鳥羽水族館は、絶滅危惧種のジュゴンを日本で唯一見ることができる水族館でもあります。
ご興味があれば会いに行ってみてくださいね。
20世紀初頭には、ラッコは2000頭以下にまで減ってしまいましたが、法が制定されるなど保護活動が盛んに行われたことにより、少しずつ生息数は増え、今では10〜15万頭にまで回復しています。
一方、水族館では今後見られなくなってしまうかもしれないと言われています。
北海道でも、少しづつ野生のラッコが増えてきているようです。
広い海にぷかぷかと浮かぶ、平和なラッコたちに癒されます。
コピー・イラスト / kawe
ラッコ / 海獺 / Sea otter
水族館で人気のラッコが、絶滅危惧種?!
その可愛さからもファンが多いラッコ。
水族館などでよく見るイメージがあるかと思いますが、実はラッコは、絶滅危惧種のレッドリストの中でも絶滅の危険が非常に高い「絶滅危惧IA類」に指定されています。
水族館で見られるラッコも、今ではかなり少なくなってきています。
ラッコってどんな動物?
ラッコは、北アメリカとアジアの太平洋沿岸に生息しています。
日本では、北海道で見ることができます。
体重は約15〜45kg、体長は約100〜150cm。
平均寿命は、野生では約15年、飼育下では約20年です。
鼻はひし形で、尾は平べったい形。
水の中に入っているときは、鼻と耳を閉じることができます。
顔の毛の色は赤ちゃんの頃は茶色ですが、3歳を過ぎる頃から、年齢を重ねるにつれだんだん白くなっていきます。
わきの下のたるみをポケットのようにして、お気に入りの石や食べきれなかった貝などをしまいこむ癖があります。
鳥羽水族館YouTubeにわかりやすい動画がありました。
ラッコは海の沿岸部や、海岸から1km以内の場所に生息しており、一生のほとんどを海の中で過ごします。
食事をしたり眠ったりするときには、流されないように海藻を体に巻き付けたり、つかまったりするそうです。
ラッコ同士、手を繋いで休むことも。
水族館でも手を繋いでいる姿は大人気。誰もがメロメロになってしまう可愛さですね。
ラッコは食いしん坊?
ラッコは肉食で、主に貝類や甲殻類、ウニ類などを食べます。魚類や海鳥を食べることもあります。
皮下脂肪が少ないため、体温を維持するために1日に体重の約4分の1〜5分の1の量の食べ物を食べる必要があります。
ラッコは30kgほどなので、1日に約6〜9kg食べなければなりません。
これは、50kgの人間に置き換えると、1日に10〜15kgも食べるということになります。
驚きの量ですが、ラッコはただの食いしん坊ではなく、生きるために食べているのですね。
そしてラッコと言えば、貝などの硬い食べ物をお腹の上に乗せた石に叩きつけて割り、中身を食べる行動が有名ですが、住む地域によっては叩きつける必要がないものを食べるため、この行動をしないラッコもいます。
水族館では、展示用のガラスや石に叩きつけて割ることも多いようですが、なんと2009年には、愛知県の豊橋総合動植物公園で飼育されていたラッコのヤヨイ(メス・15歳)が、数年にわたりエサの貝殻をガラスに打ち付けて食べていたところ、とうとうガラスも耐えられなくなり、強化ガラスであるにも関わらずヒビが入ったことがあるそうです。
ラッコの力を侮ることなかれ。。
ラッコにとって大切な、毛皮と毛づくろい
全身に約8億本もの体毛が生えているラッコ。
特にお腹の毛は、ほ乳類の中でも密度がとても高いと言われています。
ちなみに、人間の体毛は500万本、髪は10万本だそうです。ラッコ、すごい。
しかし、すごいのは毛の多さだけではありません。
毛づくろい(グルーミング)をして毛と毛の間に空気の層をつくり、冷たい水が直接皮膚に触れないようにすることで、体温を保つことができるのです。
Xで話題になったこのほっぺたをむにむにする可愛い仕草も、毛づくろいだそうです。
https://x.com/mayu_kko/status/1556097751934726145?s=20
冷たい水の中でもラッコが生きられるのは、この毛のおかげなのです。
毛が汚れてしまうと、体温をうまく調節できなくなってしまうため、ラッコは1日5〜6時間も毛づくろいをしなくてはいけません。
この優れた保温機能を求めて、毛皮を目的にラッコは世界中で乱獲されてしまいます。
日本でも平安時代から乱獲され、絶滅寸前にまで数が減ってしまいました。
そこで、明治時代の1912年には、ラッコやオットセイの捕獲を禁止する「臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)」が公布されました。
乱獲されたり、漁業の網にかかってしまったり、タンカー事故で流出した原油の被害にあったり、世界中でラッコの生息数が減ってしまった原因には、いろいろなものがあります。
現在、水族館で会えるラッコは3頭のみ!
1982年、アラスカから静岡県の「伊豆・三津シーパラダイス」に初めてラッコが来ました。
1984年に三重県の「鳥羽水族館」で日本初のラッコの赤ちゃんが誕生したことから、ラッコブームが始まったと言われています。当時は3時間の行列ができるほどの人気ぶりだったそう。
しかしその後、ラッコの個体数が減ったために、ワシントン条約で国際取引が禁止とされました。
水族館での繁殖も難しいため、日本の水族館ではラッコがどんどん減っている状況です。
ピークである1994年には122頭が飼育されていましたが、2024年1月現在、日本国内で見られるのは3頭のみとなっています。
そのうちの2頭が、三重県の「鳥羽水族館」、
1頭が、福岡県の「マリンワールド海の中道」で飼育されています。
鳥羽水族館は、絶滅危惧種のジュゴンを日本で唯一見ることができる水族館でもあります。
ご興味があれば会いに行ってみてくださいね。
20世紀初頭には、ラッコは2000頭以下にまで減ってしまいましたが、法が制定されるなど保護活動が盛んに行われたことにより、少しずつ生息数は増え、今では10〜15万頭にまで回復しています。
一方、水族館では今後見られなくなってしまうかもしれないと言われています。
北海道でも、少しづつ野生のラッコが増えてきているようです。
広い海にぷかぷかと浮かぶ、平和なラッコたちに癒されます。
コピー・イラスト / kawe
>> 続きを読む
獰猛な妖精「ホンドオコジョ」 (Fri, 19 Jan 2024)
 ホンドオコジョ / Japanese Stoat
ホンドオコジョって、どんな動物?
別名:ヤマイタチ、クダギツネ
準絶滅危惧種、そして長野県の天然記念物です。
体長は約15〜20cm。尾の長さは5〜7cm。
オコジョには35種類以上の亜種がいますが、日本の本州にはホンドオコジョ、北海道にはエゾオコジョが生息しています。
ホンドオコジョは、エゾオコジョよりも一回り小さいのが特徴で、主に東北地方や中部地方などの山岳地帯に生息しています。
遭遇する難易度はかなり高そうですが、出会えたらとてもラッキーですね!
長野県の志賀高原では、その可愛らしい姿や、めったに出会えないことから「山の妖精」と呼ばれ親しまれています。
ちなみに、志賀高原の観光PRキャラクター「おこみん」はオコジョがモチーフになっています。
https://www.shigakogen.gr.jp/okomin/index.html(志賀高原観光協会
公式Webサイト)
季節によって体毛の色が変わります。夏は茶色(お腹は白)、冬は白色になり、夏毛の時も冬毛の時も、尾の先端は黒いのが特徴です。
志賀高原と富山県で目撃された夏毛のオコジョたち。
長野県で発見された冬毛のオコジョ。
真っ白な体で、真っ白な雪の中に溶け込む姿は、まさに妖精ですね。
すばしっこいですが、愛らしく、人々が釘付けになってしまう気持ちがよくわかります。
実は気性が荒い?!
ホンドオコジョは、肉食で気性が荒いことでも知られています。
主にネズミなどの小動物や鳥類を食べたりしますが、自分よりも体の大きいノウサギやライチョウを捕食することも。
その可愛らしさとのギャップに魅力を感じる人も多いようです。
人々から愛されているホンドオコジョですが、土地の開発や森林伐採などにより生息地を奪われたり、ミンクとの生存競争により生息数が減少しています。
コピー・イラスト / kawe
ホンドオコジョ / Japanese Stoat
ホンドオコジョって、どんな動物?
別名:ヤマイタチ、クダギツネ
準絶滅危惧種、そして長野県の天然記念物です。
体長は約15〜20cm。尾の長さは5〜7cm。
オコジョには35種類以上の亜種がいますが、日本の本州にはホンドオコジョ、北海道にはエゾオコジョが生息しています。
ホンドオコジョは、エゾオコジョよりも一回り小さいのが特徴で、主に東北地方や中部地方などの山岳地帯に生息しています。
遭遇する難易度はかなり高そうですが、出会えたらとてもラッキーですね!
長野県の志賀高原では、その可愛らしい姿や、めったに出会えないことから「山の妖精」と呼ばれ親しまれています。
ちなみに、志賀高原の観光PRキャラクター「おこみん」はオコジョがモチーフになっています。
https://www.shigakogen.gr.jp/okomin/index.html(志賀高原観光協会
公式Webサイト)
季節によって体毛の色が変わります。夏は茶色(お腹は白)、冬は白色になり、夏毛の時も冬毛の時も、尾の先端は黒いのが特徴です。
志賀高原と富山県で目撃された夏毛のオコジョたち。
長野県で発見された冬毛のオコジョ。
真っ白な体で、真っ白な雪の中に溶け込む姿は、まさに妖精ですね。
すばしっこいですが、愛らしく、人々が釘付けになってしまう気持ちがよくわかります。
実は気性が荒い?!
ホンドオコジョは、肉食で気性が荒いことでも知られています。
主にネズミなどの小動物や鳥類を食べたりしますが、自分よりも体の大きいノウサギやライチョウを捕食することも。
その可愛らしさとのギャップに魅力を感じる人も多いようです。
人々から愛されているホンドオコジョですが、土地の開発や森林伐採などにより生息地を奪われたり、ミンクとの生存競争により生息数が減少しています。
コピー・イラスト / kawe
>> 続きを読む
外来種だけど絶滅危惧?!対馬の「シベリアイタチ」 (Mon, 15 Jan 2024)
 シベリアイタチ / Siberian weasel
シベリアイタチってどんな動物?
別名:タイリクイタチ、チョウセンイタチ、コウライイタチ
在来種のニホンイタチと似ており、西日本の方でもたびたび目撃されるので、在来種と思われがちですが、彼らはれっきとした外来種です。
ニホンイタチに比べて体は一回り大きく、長い尾が特徴です。
環境省より、ニホンイタチとシべリアイタチ(チョウセンイタチ)の見分け方の解説が出ています。
チョウセンイタチ及びコウノトリの見分け方(pdf)
体長は、オスが28-39cm、メスが25-31cm
尾の長さは、オスが16-21cm、メスが13-16cm
体重は650-820g、メスが360-430gです。
オスの方がメスよりも大きく、オスの体重はメスの体重の2倍もあります。
ミャンマー北部、ラオス、北朝鮮、パキスタン、ネパール、インド、ブータン、ロシアの一部、台湾、タイ北部、西日本など広範囲に生息しています。
冬の毛皮はとても密度が高く、柔らかくふわふわです。そのため、毛皮を目的に乱獲されることがあります。
毛皮業者により日本へ持ちこまれたシベリアイタチが逃げ出したり、ネズミ駆除のために放たれたりしたことなどにより、西日本を中心に分布を広げています。
夜行性で、木に登ったり、水の中を泳ぐこともできます。
ネズミなどの小型の哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫、木の実、果実などを食べます。
一夫多妻制で、野生での平均寿命はおよそ1.9歳。とても短いですね。
どうして絶滅危惧種になってしまったの?
ロシア(シベリア地方)ではコリンスキーと呼ばれ、尾の体毛が高級な筆の原料として使われることがあります。
分布域が広いため、種としての絶滅の危険は低いとされていますが、乱獲や生息地の破壊、交通事故などにより生息数が減っている地域もあります。
日本では、対馬のシベリアイタチは2020年3月に絶滅危惧種に指定されています。
対馬の「シベリアイタチ」、急減で絶滅危惧種に(読売新聞)
絶滅危惧種だけど、侵略的外来種ワースト100入り
絶滅の危機に瀕している地域がある一方で、対馬以外の日本に生息するシベリアイタチの数は増加していると考えられています。
シベリアイタチは、家畜や農場への被害、家屋への侵入、騒音被害などの問題を引き起こす厄介な存在でもあり、地域によってはその被害も増えているため、日本の侵略的外来種ワースト100に指定されています。
侵略的外来種とは、外来種の中でも、地域の自然環境や生物多様性を脅かすおそれのある生物のことです。
絶滅危惧種でもあり、侵略的外来種でもあるシベリアイタチ。
そのどちらも、原因には人間が関わっています。
さらに、2022年11月には、シベリアイタチとニホンイタチの親から生まれた雑種が高校生により発見されています。
これまでシベリアイタチとニホンイタチは、染色体の形状が異なり異種交配はできないと考えられていたため、大発見だと言われています。
福井の高校生によるイタチ研究「定説覆す大発見」 在来種と外来種の交配を指摘、林野庁長官賞(福井新聞)
コピー・イラスト / kawe
シベリアイタチ / Siberian weasel
シベリアイタチってどんな動物?
別名:タイリクイタチ、チョウセンイタチ、コウライイタチ
在来種のニホンイタチと似ており、西日本の方でもたびたび目撃されるので、在来種と思われがちですが、彼らはれっきとした外来種です。
ニホンイタチに比べて体は一回り大きく、長い尾が特徴です。
環境省より、ニホンイタチとシべリアイタチ(チョウセンイタチ)の見分け方の解説が出ています。
チョウセンイタチ及びコウノトリの見分け方(pdf)
体長は、オスが28-39cm、メスが25-31cm
尾の長さは、オスが16-21cm、メスが13-16cm
体重は650-820g、メスが360-430gです。
オスの方がメスよりも大きく、オスの体重はメスの体重の2倍もあります。
ミャンマー北部、ラオス、北朝鮮、パキスタン、ネパール、インド、ブータン、ロシアの一部、台湾、タイ北部、西日本など広範囲に生息しています。
冬の毛皮はとても密度が高く、柔らかくふわふわです。そのため、毛皮を目的に乱獲されることがあります。
毛皮業者により日本へ持ちこまれたシベリアイタチが逃げ出したり、ネズミ駆除のために放たれたりしたことなどにより、西日本を中心に分布を広げています。
夜行性で、木に登ったり、水の中を泳ぐこともできます。
ネズミなどの小型の哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫、木の実、果実などを食べます。
一夫多妻制で、野生での平均寿命はおよそ1.9歳。とても短いですね。
どうして絶滅危惧種になってしまったの?
ロシア(シベリア地方)ではコリンスキーと呼ばれ、尾の体毛が高級な筆の原料として使われることがあります。
分布域が広いため、種としての絶滅の危険は低いとされていますが、乱獲や生息地の破壊、交通事故などにより生息数が減っている地域もあります。
日本では、対馬のシベリアイタチは2020年3月に絶滅危惧種に指定されています。
対馬の「シベリアイタチ」、急減で絶滅危惧種に(読売新聞)
絶滅危惧種だけど、侵略的外来種ワースト100入り
絶滅の危機に瀕している地域がある一方で、対馬以外の日本に生息するシベリアイタチの数は増加していると考えられています。
シベリアイタチは、家畜や農場への被害、家屋への侵入、騒音被害などの問題を引き起こす厄介な存在でもあり、地域によってはその被害も増えているため、日本の侵略的外来種ワースト100に指定されています。
侵略的外来種とは、外来種の中でも、地域の自然環境や生物多様性を脅かすおそれのある生物のことです。
絶滅危惧種でもあり、侵略的外来種でもあるシベリアイタチ。
そのどちらも、原因には人間が関わっています。
さらに、2022年11月には、シベリアイタチとニホンイタチの親から生まれた雑種が高校生により発見されています。
これまでシベリアイタチとニホンイタチは、染色体の形状が異なり異種交配はできないと考えられていたため、大発見だと言われています。
福井の高校生によるイタチ研究「定説覆す大発見」 在来種と外来種の交配を指摘、林野庁長官賞(福井新聞)
コピー・イラスト / kawe
>> 続きを読む
未来を予測するサル「ピグミーマーモセット」 (Wed, 10 Jan 2024)
 ピグミーマーモセット / Pygmy marmoset
ピグミーマーモセットってどんな動物?
ピグミーマーモセットは、エクアドル、コロンビア、ブラジルなどの南米に生息しています。
体長は約12-16センチメートル。尻尾の長さは約20センチメートル。
体重は約80-140グラム。リンゴよりも軽い!
顔の大きさは五百円玉硬貨と同じ大きさだそうです。
↓500円玉と比較した画像(日本モンキーセンター公式X)
https://x.com/j_monkeycentre/status/1159015283136184320?s=20
1998年までは、世界最小のサルと言われていました。
現在の世界最小のサルは「ピグミーキツネザル」で、マダガスカルの西部に生息しています。
ピグミーキツネザルについては今のところ情報が少なく、生息数や詳しい生態などは不明なようです。
何を食べるの?
ピグミーマーモセットは雑食です。
昆虫や果実なども食べますが、主食は樹液です。
樹液を食べて生きているとは、なんと可愛い動物なのでしょうか。。
実は、樹液の食べ方は少し変わっています。
まず木の表皮を歯で削って樹液が出る状態にしておき、翌日、そこから滲み出て十分に溜まった樹液を舐めます。
このように、先を予測した行動をとる動物は、人間以外ではとても珍しいと言われています。
1:05〜 樹液を食べるピグミーマーモセット
ピグミーマーモセットは、その可愛さからペットとして人気があります。
森林伐採などにより生息地を奪われたり、食用、ペット用に狩猟されることにより生息数が減ってしまっています。
現在、日本でピグミーマーモセットを見られる場所も少なくなってきています。
1つ目は「草津熱帯園」
そして、「神戸どうぶつ王国」
こちらの2ヶ所のみです。
いつか、日本で見られなくなってしまうこともあるかもしれません。
最後に、筆者のイチオシ動画です。
ピグミーマーモセット / Pygmy marmoset
ピグミーマーモセットってどんな動物?
ピグミーマーモセットは、エクアドル、コロンビア、ブラジルなどの南米に生息しています。
体長は約12-16センチメートル。尻尾の長さは約20センチメートル。
体重は約80-140グラム。リンゴよりも軽い!
顔の大きさは五百円玉硬貨と同じ大きさだそうです。
↓500円玉と比較した画像(日本モンキーセンター公式X)
https://x.com/j_monkeycentre/status/1159015283136184320?s=20
1998年までは、世界最小のサルと言われていました。
現在の世界最小のサルは「ピグミーキツネザル」で、マダガスカルの西部に生息しています。
ピグミーキツネザルについては今のところ情報が少なく、生息数や詳しい生態などは不明なようです。
何を食べるの?
ピグミーマーモセットは雑食です。
昆虫や果実なども食べますが、主食は樹液です。
樹液を食べて生きているとは、なんと可愛い動物なのでしょうか。。
実は、樹液の食べ方は少し変わっています。
まず木の表皮を歯で削って樹液が出る状態にしておき、翌日、そこから滲み出て十分に溜まった樹液を舐めます。
このように、先を予測した行動をとる動物は、人間以外ではとても珍しいと言われています。
1:05〜 樹液を食べるピグミーマーモセット
ピグミーマーモセットは、その可愛さからペットとして人気があります。
森林伐採などにより生息地を奪われたり、食用、ペット用に狩猟されることにより生息数が減ってしまっています。
現在、日本でピグミーマーモセットを見られる場所も少なくなってきています。
1つ目は「草津熱帯園」
そして、「神戸どうぶつ王国」
こちらの2ヶ所のみです。
いつか、日本で見られなくなってしまうこともあるかもしれません。
最後に、筆者のイチオシ動画です。



 ピグミーマーモセットのグッズはSUZURIにて販売中です!
コピー・イラスト / kawe
ピグミーマーモセットのグッズはSUZURIにて販売中です!
コピー・イラスト / kawe
>> 続きを読む