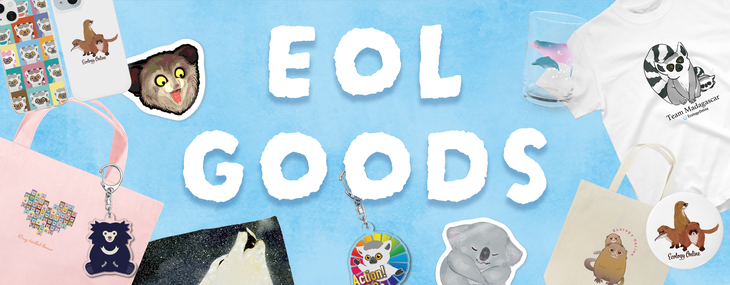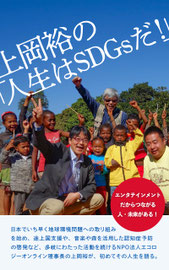アイアイ / Aye-Aye
マダガスカルに生息する。
アイアイ科アイアイ属に分類される唯一の現生種。
耳が大きく、指が細長いのが特徴。特に中指が長い。
夜行性の霊長類であり、
木に住み着いた害虫なども、細長い中指でほじくり出して食べてくれる。
マダガスカルの現地では『悪魔の化身』と恐れられ、駆除されることもある。
「アイアイ」と調べると怖い写真ばかり出てくるが、「Aye-Aye」と調べると、怖いだけではないということがお分かりいただけるだろう。
売り上げの一部はエコロジーオンラインの活動に寄付されます。
コピー・イラスト / kawe
www.eco-online.org Blog Feed
ケープペンギン大量死の悲劇!主食の魚が消え、「飢餓」が群れを襲った (土, 06 12月 2025) Photo by Hongbin on Unsplash
南アフリカ沖に生息するケープペンギンは、その愛らしい姿とは裏腹に、今、種の存続の危機に瀕している。2024年には絶滅寸前種(Critically
Endangered)に分類されたこのペンギンたちの個体数が、特に2004年以降、急速に減少した背景には、「食料不足による飢餓」が深く関わっているという、衝撃的な研究結果が発表された。ダッセン島やロベン島といった重要な繁殖地では、わずか8年間で繁殖個体の最大95パーセントが死亡したと推定されている。
なぜペンギンたちは飢えたのか?
ペンギンたちの主食は、イワシ(サーディン)である。研究によると、2004年から2011年の間、南アフリカ西海岸沖のイワシの資源量が、ピーク時の25パーセント以下という極めて低い水準で推移していたことが、大量死の主要な原因であると考えられている。
ペンギンは毎年、古い羽毛を新しいものに生え替えるために換羽を行う。この換羽期間(約21日間)は、羽毛の防水性が失われるため、ペンギンは陸上でじっとしている必要があり、一切狩りに出ることができない。彼らはこの絶食期間を乗り切るため、事前にたっぷりと脂肪を蓄えておかねばならない。もし、換羽の前に十分な食料を見つけられなかったり、換羽直後に体力を回復させるための餌が不足したりすれば、彼らは自らの蓄えだけで生き延びることができず、飢餓によって命を落としてしまう。この数十年間に、まさにこの危機が頻繁に起こっていたのだ。
気候変動と人間の活動が招いた複合的な危機
イワシの資源量が激減した背景には、二つの要因が複合的に作用している。一つは、産卵場所周辺の海水温や塩分の変化といった環境変動である。もう一つは、人間の漁業活動だ。イワシの資源量が減少しているにもかかわらず、過去の産業構造の影響で、漁業活動の多くがペンギンの重要な採餌エリアである西海岸沖に残ってしまった。資源が少ない状況で、漁獲率が非常に高くなったことが、ペンギンたちの食料不足をさらに深刻化させ、大量死を引き起こしたと考えられている。
生き残りのための「管理戦略」
研究チームは、アホウドリの食料状況のデータなど、さまざまな指標を用いてペンギンたちの生存率を分析し、大人のペンギンの生存率が、まさに餌の入手可能性に強く関係していることを証明した。特に、最も危険な時期である換羽期の生存率が餌に左右されていたのである。
この悲劇的な研究結果は、ケープペンギンを絶滅から救うための管理戦略の重要性を強く示している。ペンギンたちの長期的な生存を確実にするためには、餌となるイワシの資源量を回復させることが不可欠である。漁獲量が最大値の25パーセント未満になった際には、漁獲を減らすなど、漁業管理の方法を改善することが求められている。
すでに、最大の繁殖コロニー周辺での商業的なまき網漁が禁止されるなど、ペンギンを直接保護するための措置も講じられている。研究者たちは、これらの措置と漁業管理の改善とが組み合わされることで、ケープペンギンがこの危機を乗り越え、回復の兆しを見せることを強く望んでいる。
<関連サイト>
High adult mortality of African Penguins Spheniscus
demersus in South Africa after 2004 was likely caused by starvation
翻訳・文 / エコロジーオンライン編集部(AIを使用)
Photo by Hongbin on Unsplash
南アフリカ沖に生息するケープペンギンは、その愛らしい姿とは裏腹に、今、種の存続の危機に瀕している。2024年には絶滅寸前種(Critically
Endangered)に分類されたこのペンギンたちの個体数が、特に2004年以降、急速に減少した背景には、「食料不足による飢餓」が深く関わっているという、衝撃的な研究結果が発表された。ダッセン島やロベン島といった重要な繁殖地では、わずか8年間で繁殖個体の最大95パーセントが死亡したと推定されている。
なぜペンギンたちは飢えたのか?
ペンギンたちの主食は、イワシ(サーディン)である。研究によると、2004年から2011年の間、南アフリカ西海岸沖のイワシの資源量が、ピーク時の25パーセント以下という極めて低い水準で推移していたことが、大量死の主要な原因であると考えられている。
ペンギンは毎年、古い羽毛を新しいものに生え替えるために換羽を行う。この換羽期間(約21日間)は、羽毛の防水性が失われるため、ペンギンは陸上でじっとしている必要があり、一切狩りに出ることができない。彼らはこの絶食期間を乗り切るため、事前にたっぷりと脂肪を蓄えておかねばならない。もし、換羽の前に十分な食料を見つけられなかったり、換羽直後に体力を回復させるための餌が不足したりすれば、彼らは自らの蓄えだけで生き延びることができず、飢餓によって命を落としてしまう。この数十年間に、まさにこの危機が頻繁に起こっていたのだ。
気候変動と人間の活動が招いた複合的な危機
イワシの資源量が激減した背景には、二つの要因が複合的に作用している。一つは、産卵場所周辺の海水温や塩分の変化といった環境変動である。もう一つは、人間の漁業活動だ。イワシの資源量が減少しているにもかかわらず、過去の産業構造の影響で、漁業活動の多くがペンギンの重要な採餌エリアである西海岸沖に残ってしまった。資源が少ない状況で、漁獲率が非常に高くなったことが、ペンギンたちの食料不足をさらに深刻化させ、大量死を引き起こしたと考えられている。
生き残りのための「管理戦略」
研究チームは、アホウドリの食料状況のデータなど、さまざまな指標を用いてペンギンたちの生存率を分析し、大人のペンギンの生存率が、まさに餌の入手可能性に強く関係していることを証明した。特に、最も危険な時期である換羽期の生存率が餌に左右されていたのである。
この悲劇的な研究結果は、ケープペンギンを絶滅から救うための管理戦略の重要性を強く示している。ペンギンたちの長期的な生存を確実にするためには、餌となるイワシの資源量を回復させることが不可欠である。漁獲量が最大値の25パーセント未満になった際には、漁獲を減らすなど、漁業管理の方法を改善することが求められている。
すでに、最大の繁殖コロニー周辺での商業的なまき網漁が禁止されるなど、ペンギンを直接保護するための措置も講じられている。研究者たちは、これらの措置と漁業管理の改善とが組み合わされることで、ケープペンギンがこの危機を乗り越え、回復の兆しを見せることを強く望んでいる。
<関連サイト>
High adult mortality of African Penguins Spheniscus
demersus in South Africa after 2004 was likely caused by starvation
翻訳・文 / エコロジーオンライン編集部(AIを使用)
>> 続きを読む
アザラシと鳥たちが告げる気候と生物多様性の危機 (Sun, 12 Oct 2025)
 Photo by Kerin Gedge on Unsplash
IUCN(国際自然保護連合)の絶滅危惧種レッドリストの最新版が発表され、地球の生命の多様性がどれほど深刻な危機に瀕しているかが明らかになった。気候変動は決して遠い未来の問題ではなく、この瞬間にも私たちの大切な生き物たちの命を脅かしている。
特に懸念されるのが、北極のアザラシたちだ。地球温暖化の進行により、北極では他の地域よりも4倍も速いペースで海氷が溶けている。アザラシたちは、繁殖、子育て、休息、そして餌を探すためにこの海氷に完全に頼って生きている。しかし、頼みの綱である海氷が薄くなり、消えてしまうことで、彼らの生活は根本から破壊されつつある。その結果、ズキンアザラシは「危急」から「危機」に、アゴヒゲアザラシとタテゴトアザラシも「軽度懸念」から「準絶滅危惧」に、それぞれ絶滅の危険度が引き上げられた。
このアザラシたちの窮状は、気候変動が生態系の均衡をいかに大きく崩しているかを痛切に示している。彼らはホッキョクグマなどの重要な食料源であり、海洋の食物連鎖の中心を担う「キーストーン種」であるため、彼らが失われることは、北極圏全体の生態系に計り知れない影響を与えるのである。
一方、世界の鳥類の状況も芳しくない。バードライフ・インターナショナルによる最新の包括的評価によると、世界の鳥類の61%が個体数減少の傾向にあるという。この割合は2016年の44%から大幅に増加しており、生物多様性の危機が加速している証拠である。鳥類減少の最大の原因は、生息地の喪失と劣化であり、特にマダガスカルや西アフリカ、中央アメリカといった熱帯林の伐採が、固有の鳥類を絶滅の淵へと追いやっている。
鳥類は、私たちが思っている以上に大切な役割を担っている。彼らは花粉を運び、種子を散布し、害虫を駆除するなど、生態系の健全性を保つ「エンジニア」として機能している。熱帯林における鳥たちの働きは、森林の再生や地球の炭素貯蔵に不可欠であり、彼らを失うことは、気候危機と生物多様性危機が深く絡み合っていることを示している。
しかし、希望の光もある。数十年にわたる集中的な保護活動の結果、アオウミガメの世界的個体数は回復傾向にあり、絶滅危惧種から「軽度懸念種」へと改善された。これは、人間が強い決意と団結をもって行動すれば、自然の回復を助けることができるという、力強い証しである。
IUCN事務局長が述べるように、このレッドリストの更新は、私たちに「行動を加速させる決定的な機会」が訪れていることを教えてくれる。アオウミガメの成功例に学び、北極のアザラシや世界の鳥類を守るため、今こそ気候変動対策と生物多様性保全の行動を、私たちの生活の中心に据える必要があるのだ。
<関連サイト>
気候変動で北極のアザラシが危機に、世界の鳥類は減少傾向-IUCNレッドリスト
翻訳・文 / エコロジーオンライン編集部(AIを使用)
Photo by Kerin Gedge on Unsplash
IUCN(国際自然保護連合)の絶滅危惧種レッドリストの最新版が発表され、地球の生命の多様性がどれほど深刻な危機に瀕しているかが明らかになった。気候変動は決して遠い未来の問題ではなく、この瞬間にも私たちの大切な生き物たちの命を脅かしている。
特に懸念されるのが、北極のアザラシたちだ。地球温暖化の進行により、北極では他の地域よりも4倍も速いペースで海氷が溶けている。アザラシたちは、繁殖、子育て、休息、そして餌を探すためにこの海氷に完全に頼って生きている。しかし、頼みの綱である海氷が薄くなり、消えてしまうことで、彼らの生活は根本から破壊されつつある。その結果、ズキンアザラシは「危急」から「危機」に、アゴヒゲアザラシとタテゴトアザラシも「軽度懸念」から「準絶滅危惧」に、それぞれ絶滅の危険度が引き上げられた。
このアザラシたちの窮状は、気候変動が生態系の均衡をいかに大きく崩しているかを痛切に示している。彼らはホッキョクグマなどの重要な食料源であり、海洋の食物連鎖の中心を担う「キーストーン種」であるため、彼らが失われることは、北極圏全体の生態系に計り知れない影響を与えるのである。
一方、世界の鳥類の状況も芳しくない。バードライフ・インターナショナルによる最新の包括的評価によると、世界の鳥類の61%が個体数減少の傾向にあるという。この割合は2016年の44%から大幅に増加しており、生物多様性の危機が加速している証拠である。鳥類減少の最大の原因は、生息地の喪失と劣化であり、特にマダガスカルや西アフリカ、中央アメリカといった熱帯林の伐採が、固有の鳥類を絶滅の淵へと追いやっている。
鳥類は、私たちが思っている以上に大切な役割を担っている。彼らは花粉を運び、種子を散布し、害虫を駆除するなど、生態系の健全性を保つ「エンジニア」として機能している。熱帯林における鳥たちの働きは、森林の再生や地球の炭素貯蔵に不可欠であり、彼らを失うことは、気候危機と生物多様性危機が深く絡み合っていることを示している。
しかし、希望の光もある。数十年にわたる集中的な保護活動の結果、アオウミガメの世界的個体数は回復傾向にあり、絶滅危惧種から「軽度懸念種」へと改善された。これは、人間が強い決意と団結をもって行動すれば、自然の回復を助けることができるという、力強い証しである。
IUCN事務局長が述べるように、このレッドリストの更新は、私たちに「行動を加速させる決定的な機会」が訪れていることを教えてくれる。アオウミガメの成功例に学び、北極のアザラシや世界の鳥類を守るため、今こそ気候変動対策と生物多様性保全の行動を、私たちの生活の中心に据える必要があるのだ。
<関連サイト>
気候変動で北極のアザラシが危機に、世界の鳥類は減少傾向-IUCNレッドリスト
翻訳・文 / エコロジーオンライン編集部(AIを使用)
>> 続きを読む